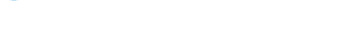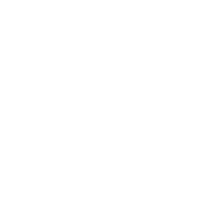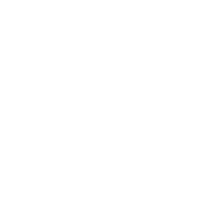目次
サインバルタの可能性を学ぶ
今日は昨日のDJ明けに、睡眠不足になりながらも東京まで勉強に来ました。
慢性の痛みに対するお薬、サインバルタの勉強会です。講演でお話された内容と、私見を加えてご紹介させていただきます。
※この記事は2017年時点での講演内容をもとにしています。
サインバルタは、これまで糖尿病性神経障害、線維筋痛症、慢性腰痛症といった疼痛に使用されてきたが、今回変形性関節症に適応が拡大されました。
慢性疼痛に対するサインバルタの効能
【OARSI 世界変形性関節症会議】
NSAIDsの課題。胃粘膜障害、心血管障害、腎機能障害→セレコックスといえど、長期投与は避けること。Acetaminophenカロナール、トラマドール(トラムセット、トラマール)などを使用することが循環器学会からも推奨されている。
・OA膝の20%に滑膜炎
・OA軟骨はPGE2mRNA発現が亢進
股関節OA患者 帯状回全部、島皮質の萎縮があったものが、THA後に回復したエビデンス。慢性疼痛が慢性疼痛を作る。
3か月以上続くOA治療にはNSAIDsではなく、中枢感作を改善するサインバルタを。
下降性疼痛抑制系の機能異常を改善する必要があり、サインバルタで下降性疼痛抑制系を賦活化する。
炎症の有無にかかわらず痛みを感じている患者さんはサインバルタの適応。
サインバルタはうつ症状の改善よりも下降性疼痛抑制系の賦活作用が作用機序。
下降性疼痛抑制系は人研究においてエビデンスを示すことは難しいが、薬物使用により改善されている事実により間接的に下降性疼痛抑制系に働いていることを推測している。
弱オピオイドとの使い分けはリスクとベネフィットから考える。
→ここは実際に僕もサインバルタとトラマール、トラマドールをたくさん使用していますが、使い分けについては明確な基準は難しいですね。
サインバルタはもともと鬱に対する薬でもあるため、気分の抑うつ傾向のある患者さんにはとてもよく効く印象があります。
慢性疼痛患者の脳の中でセロトニンやノルアドレナリンのレベルがどうなっているのかはまだ分かっていない。
サインバルタの作用の95%は脳ではなく、脊髄後核で効いているといわれている。
昔から下降性疼痛抑制系賦活薬として使われているノイロトロピンも作用機序は詳細にわかっていない。今後の課題。
→慢性疼痛の治療がここ数年急速に脚光を浴びる中で、下降性疼痛抑制系などの人間が本来持つ内因性の疼痛コントロール作用について今後もっと解明されてくることが期待されますね。
発展の余地がまだまだたくさんある、とても勉強が楽しい分野です。
サインバルタの臨床経験に基づいたデータ
症状改善と副作用
医療法人全心会 寝屋川ひかり病院 整形外科 習田武史先生
サインバルタ200症例の臨床経験
3か月以上持続する慢性腰痛患者(下肢症状を有する患者を含む)
BPI (0-10)
RDQ24 Rolland Morris Disability Questionnaire 腰痛特異的QOL尺度
サインバルタはRDQ24を劇的に改善させた。
【改善率】
著明改善…8.4%
改善…55.4%
やや改善…28.2%
不変…7.9%
やや悪化…0%
悪化…0%
【継続率】
継続率…85.9%(195人)
中止…32人中、副作用中止は6人のみ。
60㎎(20㎎×3錠)を6か月使用した患者46人にて、BPI…7.1→2.4 RDQ24…9.2→3.4と劇的に改善。
主な副作用は増量中に悪心、傾眠、口喝が3人に1人。
便秘は6.5%(3人のみ)。
倦怠感は4.3%(2人のみ)。
口喝は6か月経過後も19.6%→9例で継続した。
投与初期に制吐剤を併用することで、悪心は12%→9人に1人に低下。
症状に対する治療方法
我々はレントゲンの形を整えるのではなく、患者さんの求めるニーズをどうやって満たすのか考える必要がある。
変形性関節症は分子メカニズムがわかっていないため、原因療法はなく、対症療法でしかない。
→僕は変形の原因は軟部組織による骨付着部への影響と、その患者さんの骨リモデリング能力だと考えています。
短縮した筋肉や、コリを放置したままでいることで、持続的に骨を牽引し続けることが関節変形につながるリモデリングを引き起こしているのでしょう。
そのため、コリを早くほぐして関節に対する軟部組織ストレスを適切なバランスに整えておくことが大切ですね。
変形性関節症は関節リウマチのような全身疾患ではない。サインバルタだけの治療は考えられず、局所のヒアルロン酸などの治療との併用が必要である。
→やはり関節内に病変があるという考えからは逃れられないようですね。変形自体は問題ではない。
慢性の痛みに対して中枢感作を起こしてしまい、疼痛閾値が下がった患者さんに対してはサインバルタが必要ですが、膝関節内への局所治療が必ずしも必要なわけではなく、痛みが膝関節内からきているのか、関節外の軟部組織の異常MPSからきているものなのかを常に考えることが必要ですね。
滑膜炎や結晶性関節炎、関節リウマチなどの炎症性疾患や腫瘍、骨壊死などの疾患を除外すれば、変形自体は痛みの大きな原因となっていることは少なく、ほとんどの痛みは関節内ではなく、MPSだと考えています。
慢性疼痛の治療で重要なこと
Opening Remarks 福島県立医科大学 紺野愼一先生
最近のfMRIなどの研究により、下降性疼痛抑制系の機能回復が重要ということがわかってきた。
慢性腰痛の治療について、現在の医師の治療に満足しているのは9.1%。
ある程度満足は33.1%に過ぎない。
ゴール設定することで満足度は上がる。変形性関節症でも同様。
各々の患者さんの治療目標、ゴール設定を行い、ひとつずつクリアすることでQOLを上げていくことが重要。
高知大学 整形外科 池内昌彦先生
Q. OAに伴う疼痛の薬剤選択は、炎症を軽減する治療に加えて、下降性疼痛抑制系の機能減弱も考慮すべきか?
【会場アンケート結果】
同意する…47%
やや同意する…35%
あまり思わない…9%
→僕は慢性の痛みに対しては下降性疼痛抑制系の制御はとても大切だと思っています。(‘ω’)ノ
レントゲン上で膝関節の変形を持っている人の2/3は痛くない。軟骨には痛みを感知する神経はない。MRIでは滑膜炎(OR9.2)や骨髄病変(OR3.2)に痛みの原因があるとされる研究が出てきている。
高位脛骨骨切り術後には滑膜炎や骨髄病変がなくなることが知られている。
140例のKL4のOA患者さん(30か月後)
滑膜炎の改善…4%
悪化…10%
骨髄病変の改善…21%
悪化…33%
無症候性MRI所見 ひざ痛のないレントゲン変化もない50歳以上 489人
軟骨損傷…43%
骨髄病変…15%
骨棘…13%
半月損傷…10%
滑膜炎…4%(2012)
なかなか痛みの原因と画像所見は結びついていない。局所だけでなく、神経系の変化を考える必要がある。痛みは脳で認知する。
滑膜炎や骨髄病変からの末梢感作sensitization、中枢感作 central sensitization、下降性疼痛抑制系の機能不全などが考えられる。
医学部の勉強では痛覚、痛みについての勉強はほとんどない。
痛覚伝導路 外側脊髄視床路 体性感覚野・・・感覚
内側脊髄網様体路 帯状回、島・・・情動
中脳中心灰白質 PAG、大縫線核 NRM、、、下降性疼痛調節系
PAGを刺激するとラットで麻酔薬なしで手術ができた。
内因性鎮痛機序
脊髄攻核介在ニューロン・・・ゲートコントロール理論
下降性疼痛調節系 5HT、NAd作動性ニューロン
内因性オピオイド
広範性侵害抑制調節系
中枢感作の指標 時間的荷重 temporal summation
爪を押して痛みを出す。繰り返し一定の間隔で刺激すると痛みが強くなっていく。
変形性股関節症患者で、THAを受けた後に痛みが残っている患者では中枢感作が関与している可能性
→中枢を考えることも大事ですが、筋筋膜による痛み(MPS)が残っているのではないか、痛みを発していたのはもともと股関節の変形ではなかったかと考える必要があると思いますが、その点については触れられていませんでした。
中枢感作を示唆する症状所見・痛みの特徴
夜間、安静時痛:広範囲痛、長引く痛み、鎮痛薬に反応しない
不定愁訴:抑うつ、不眠、イライラ、光や音に過敏
圧痛閾値が低い
神経障害性疼痛スコア高値
→MPSが適切に処置されず、サテライトトリガーポイントが増えてしまうこと、自律神経系の調節機能低下(交感神経↑、副交感神経↓)で説明可能。
症候性の変形性膝関節症800万人→TKA8万人
痛みは局所で起こっている。侵害受容性疼痛、炎症性疼痛だから、炎症を取ってやればよい。
→これはすべてのOAでは言えない。痛み=炎症という古い疼痛モデルから脱却できていません。
レントゲン上OAがあっても、痛みの原因がOAや炎症ではない、関節外からくる軟部組織MPSの痛みについて全く触れられていません。
JOA日本整形外科学会の推奨では、推奨A NSAIDs、COX2inhibitor
→長期に連用すると胃潰瘍や腎機能低下につながるNSAIDsやCPX2inhibitorを推奨Aにしているところはさみしいですね。
慢性の痛みに対しては最初から胃潰瘍や腎機能障害のない薬剤を使用したいものです。NSAIDsは特に痛みが強い時だけのレスキューでよいと思います。
患者目線で考える”QOL”の向上
OAの痛みは、主として滑膜炎や骨髄病変などによる侵害受容性疼痛で、疼痛感作によって増幅される。
NSAIDsやヒアルロン酸などの局所療法が主流であったが、神経系に作用し、疼痛感作を減弱させる薬剤選択が可能となった。
→OAの痛みは侵害受容性疼痛・・・これは一面にすぎません。OAと思われてしまっている軟部組織の疼痛を診断できる先生がまだまだいません。
疼痛感作を減弱させる薬・・・これは慢性疼痛治療すべてに共通して重要だと思います。
島根大学 整形外科 内尾祐司先生
Q. 現在のOA治療の疼痛管理に対して、どの程度満足しているか。
【会場Drアンサーパッド】
満足している…3%
やや満足…38%
満足していない…6%
→医師もなかなか満足していないみたいですね。ヒアルロン酸の関節注射やNSAIDsで痛みを抑えるだけでは膝の痛みは取れません。
レントゲン上の膝OA…2530万人
そのうち痛みを伴う人…780万人
要支援、要介護の原因疾患として、関節疾患は10%(67.5万人)。
変形性関節症による痛みでは、階段の上り下り、掃除洗濯料理などに支障がある人、普段通りの生活ができない人が60%以上。
→それは本当に変形性関節症の痛みですか?軟部組織MPSによる痛みを除外できなければ、それが変形による痛みとは言えません。
TKA人工膝関節置換術後にも膝痛が15~20%の人に残った。OAでは慢性的な侵害刺激により、中枢感作が起こる。
86%の医師が、OAによる痛みは主に炎症を伴う侵害受容性疼痛であるととらえている。下降性疼痛抑制系の機能異常を選択する医師は35%程度。
今後の治療に必要なのは?
痛みの治療に満足していない患者は、治療法を変えても痛みは取れないと思っている人が30%以上いる。どのようなADL障害を持っているのか、医師が十分に把握していない。
痛みの原因は、加齢のせいや筋肉の衰えと説明されてしまっている。患者は治らないという印象を持ってしまう。医師が思ったほど、患者の認識を医師が把握していない。
治療ゴールを共有することが大切。
今後の治療に必要なことは、、、
痛み→力が入らない→動けない→安静にする→筋力が弱る→軟骨がすり減る→また痛む
という悪循環を断ち切ることが必要。
→これは全くその通りですね。すべての慢性疼痛治療に言えることです。
患者の満足度につながる治療を
本日のシンポジウムでは、痛みという共通の敵に対して、患者と医師が協力して立ち向かおう。患者さんの痛みに対する治療満足度を上げられる治療をしよう。
と締めくくられていました。